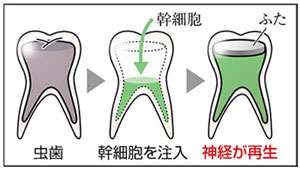47(よんなな)NEWS http://www.47news.jp/feature/medical/2012/12/post-796.html
患者を副作用から守るためのスマートフォン(多機能携帯電話)アプリ「副作用シグナルCHECKER」を製薬会社の日本ベーリンガーインゲルハイム (東京)が開発し、薬剤師ら医療者向けに無償提供を始めた。 薬の副作用を早く発見し、適切に対応するための支援ツールで、山口大病院 薬剤部長の古川裕之教授が考案した「副作用チェックシート」を基に作った。患者の自覚症状を、皮膚や目など8項目に分けて問う形式。確認した結果を電子メールで送信すれば、薬局と病院で情報を共有できる。 山口大病院と地域の薬局で1年間試験運用したところ、副作用シグナルが約1200件あり、うち93件は処方医に連絡した。同社ウェブサイトでダウンロードできる。
>>>早速、インストールしてみました。 Google Play Store(Android Market)からダウンロードできます。起動すると「氏名」「生年月日」「性別」を聞かれます。その後、具体的な症状を入力() 患者を副作用から守るためのスマートフォン(多機能携帯電話)アプリ「副作用シグナルCHECKER」を製薬会社の日本ベーリンガーインゲルハイム (東京)が開発し、薬剤師ら医療者向けに無償提供を始めた。 薬の副作用を早く発見し、適切に対応するための支援ツールで、山口大病院 薬剤部長の古川裕之教授が考案した「副作用チェックシート」を基に作った。患者の自覚症状を、皮膚や目など8項目に分けて問う形式。確認した結果を電子メールで送信すれば、薬局と病院で情報を共有できる。 山口大病院と地域の薬局で1年間試験運用したところ、副作用シグナルが約1200件あり、うち93件は処方医に連絡した。同社ウェブサイトでダウンロードできる。
>>>早速、使ってみました。
Google Play Store(Android Market)から「副作用Checksheet」をダウンロードしてインストール。起動すると「氏名」「生年月日」「性別」を聞かれるので入力。部位別に症状(例:皮膚→かゆい)を選ぶと疑われる病名が表示されます。保存すれば履歴として検索可能。
もちろんiPhone版もあります。