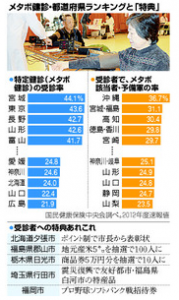http://apital.asahi.com/article/kiku/2014030400003.html
apital.asahi.com
昨年末、厚生労働省は、平成23年度(2011-2012年)の国民医療費が38兆5850億円であると発表しました。
前年度に比べ1兆1648億円、3.1%の増加となっています。
国民医療費のうち、病院や診療所で入院や外来通院に係る費用を「医科診療医療費」といい、一番大きな割合を占めています。
ちなみに、平成23年度は27兆8129億円(国民医療費全体の72.1%)となっています。
この医科診療医療費は、傷病分類別に推計額も明らかになっていて、平成23年度のトップ3は次のとおりです。
1位: 循環器系の疾患(5兆7926億円)
2位: 新生物(3兆6381億円)
3位: 呼吸器系の疾患(2兆1707億円)
そして、この傷病分類別にみると、前年比で増加率が飛び抜けて高い疾患があります。
それは、「新生物」いわゆる「がん」の領域です。
(※対前年度の増減率:循環器系疾患+2.3%、新生物+4.7%、呼吸器系疾患+2.7%)
なお、下の図は、医科診療医療費と新生物(がん)の医療費(推計額)の推移をグラフにしたものです。
2000年を基準にして金額の変化を計算してみると
医科診療医療費:23兆7960億円(2000年)→27兆8129億円(2011年)=約1.17倍
新生物(推計額):2兆808億円(2000年)→3兆6381億円(2011年)=約1.75倍
と全体の増加に比べて「新生物(がん)」の増加が高いことが分かります。
この背景には、がん患者の絶対数が増えてきていることに加えて、がんの医療現場において高額な治療法が普及してきていることも指摘されています。
たとえば、分子標的治療薬が、その代表格です。
薬の値段(薬価)だけで計算すると、1カ月あたりの費用が数十万円というのはざらで、ときに数百万円かかる場合もあります。
ただ、日本の場合は、国民皆保険制度や高額療養費制度により患者さんの負担は軽減されています。
しかし、海外に目を向けてみると状況が一変します。
米国では、国民の破産理由の約60%は、医療費が原因とされています。
英国では、国立医療技術評価機構(National Institute for Health and Clinical Excellence:NICE)が、高い価格に見合うだけの効果が得られないとして、Bevacizumab(アバスチン®)の大腸癌への「使用を推奨しない」というガイダンスを2010年12月に公表しています。
命の沙汰も金次第…。
なんだか薄ら寒いものを感じる人がいるかもしれません。
ですが、英国のこのような政策の背景には、このコラムで何回も登場してきている「科学的根拠に基づいた医療」の考え方があります。
科学的根拠に基づいた医療(Evidence-based medicine: EBM)とは、「研究によって得られた科学的根拠=エビデンス(Research evidence)、患者の価値観・意向(Patients’ preferences and actions)、医療者の専門性(Clinical expertise)、臨床現場の状況・環境(Clinical state and circumstances)の4つを考慮し、よりよい患者ケアのための意思決定を行うものである」とされています。
今回、これまで余り触れてこなかった「臨床現場の状況・環境」について少し補足します。
「臨床現場の状況・環境」において考慮しなければならない点としては、「利益(治療効果)と不利益(治療に伴う副作用)のバランス」「治療にかかるコストや資源の利用」などが挙げられています。
「利益(治療効果)と不利益(治療に伴う副作用)のバランス」については、「がん」に限らず、さまざまな疾患における診療の現場においても重要視されてきています。
皆さんも、違和感なくイメージできるかと思います。
では、「治療にかかるコストや資源の利用」についてはどうでしょうか?
先程も触れましたが、日本では、国民皆保険制度のもと、比較的安価な自己負担額で医療を受けることができるため、皆さんは、医療にかかるコストのことはあまり気にしていないかもしれません。
しかし、毎年増加し続ける国民医療費、特に高額な治療を承認すべきかどうかは、国も悩みのタネになっているようです。
最近になって、厚生労働省は、今後の医療制度の安定的な運営のために、中央社会保険医療協議会において、費用対効果評価専門部会を立ち上げ、医薬品や医療機器、医療技術を費用対効果の観点で評価する仕組みについて議論し始めています。
限られた医療資源を、どのように分配し、いかに効率よく運用していくかは、世界各国をはじめ、日本において喫緊の課題になっているようです。
それを裏付けるかのように、医学研究の分野においても、費用効果分析の論文数が右肩上がりで増えてきています。
日本人の二人に一人は罹患すると言われる「がん」。よりよい医療を受けることができるために、今後どうするべきか、どうあるべきか、国民全体で考える必要があるかもしれません
>>やはり、悪性新生物(がん)の増加の傾向を認めますが、医療も進歩しており、様々な治療の選択肢が増えてきました。その分、癌に関しての医療費の増加も認めるのは当然のことです。この記事では、海外との比較した場合、国民皆保険の制度により、対費用効果は高いことが示唆されています。そういった意味では、日本では、お金がないので治療を全く受けられないということにはならないので、この制度は改めて評価できるのではないかと考えられます。