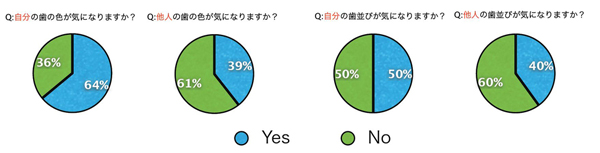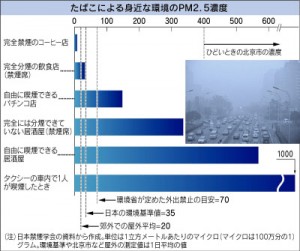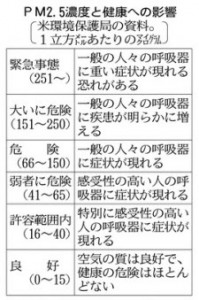YOMIURI ONLINE(兵庫) http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/hyogo/news/20130331-OYT8T01422.htm
県は2013年度から、県歯科医師会(神戸市中央区)と連携して、医師が訪問診療する「在宅歯科診療」を推進する専門部署を同会に設ける。病気や障害などで通院できないお年寄りらが、口腔(こうくう)ケア不足により、病状が悪化するケースが相次いでいることから、支援態勢を整えることにした。(東田陽介)
県医務課によると、県内の歯科は11年度末現在2966施設で、在宅診療を手がけるのはうち1割程度。持ち運びができる専門機器の調達や、歯科衛生士ら人材確保が課題になっているという。一方、在宅患者のうち、歯科診療が必要なのに、未受診者の割合は7割に達するという厚生労働省の調査(08年)もある。
お年寄りの生活の質向上のためには口腔ケアは欠かせない。口の中を清潔にしていないと、細菌が繁殖して肺炎につながったり、きちんと食べ物がかめなければ、消化不良や食欲減退を起こしたりと、命に関わる問題に発展する恐れがある。
国は10年から在宅歯科診療に取り組む自治体に補助を始め、11年度時点で32府県が機器貸し出しやPR窓口の設置に取り組んでいる。県も地元歯科医師会の要望を受け、対応を決めた。
新設するのは「在宅歯科連携室」で、県歯科医師会に委託し、設ける。同会の非常勤職員として歯科衛生士1人を配置し、在宅医療を行う歯科医の紹介や、電話で口腔ケアの指導などにあたる。
また、県内の病院などに在宅診療の実施状況を調べて現状を把握する。県は職員の人件費やPR費用などに約400万円を計上した。県の担当者は「在宅医療の必要性は、高齢化社会の進展に伴い高まるので、早急に備えたい」としている。
(2013年4月1日 読売新聞)
>>>在宅医療を推進するには、訪問の歯科保険診療をもっと充実させる必要があります。現状では、かなり制約がある中で自分の時間を割いて訪問診療を続けておられる先生もあるようで、ある意味ボランティア的な診療といえそうです。これでは、高齢者のニーズにとても答えられそうにないのではないでしょうか。