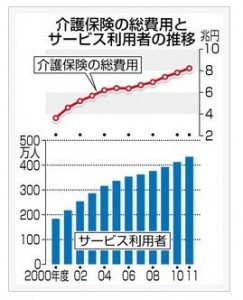http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nara/news/20130902-OYT8T01254.htm
Yomiuri.co.jp
葛城市は、小学6年生までが対象の子供の医療費助成を、来年4月から中学3年生までに拡大する方針を決めた。入院だけでなく、通院も助成するのは、県内12市では初めてという。6日開会の定例市議会に条例改正案を提案する。
同市は現在、6歳までの乳幼児医療費に加え、小学6年生までの入院と歯科診療を助成している。1医療機関あたり通院は1か月500円、入院は同1000円の自己負担が必要。
来春からは、小学生の通院、中学生の通院と入院、歯科診療も助成する。市内の中学生は約1100人おり、年間約3000万円の支出増が見込まれ、事務経費の削減などでまかなう。
山下和弥市長は「子育て世代の負担を軽減し、近い将来、経済活動を担う子供たちに多く住んでもらいたい」としている。
県によると、県内では山添村が高校卒業まで、斑鳩町など14町村が中学3年まで助成。奈良市など4市は中学生について、入院のみ助成対象にしている。
>>この試みは、非常に有意義だと思います。どの時期においても、口腔内の健康が非常に重要であるのは紛れもない事実ですが、特に中学3年生までの時期において、咬合育成の観点からも、この時期における、予防や早期治療の必要性は先生方もご存知の通りかと思いますが、家庭の経済状況などにより、治療の継続が難しい場合の問題点を解消できる策かと思います。市町村の予算の関係もあると思いますが、全国的にも是非追従してもらいたいと思います