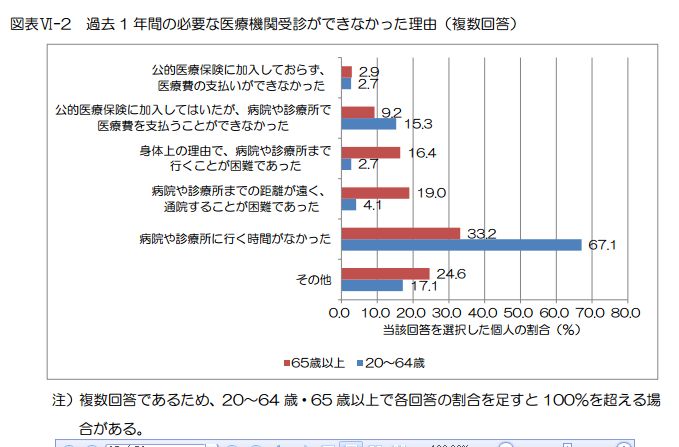http://www.ikeipress.jp/archives/6319
医療経済出版
厚生労働省は8月2日「第7回医療機関等における消費税負担に関する分科会」を開催、消費税8%引き上げ時の対応について議論を行った。日本歯科医師会からは堀憲郎常務理事が出席している。 医科、歯科、調剤への財源配分については、「それぞれの医療費シェア×それぞれの課税経費率」で按分する案がたたき台として示された。課税経費率は平成23年6月の医療経済実態調査を基に算出されており、医科25.3%、歯科33.7%、調剤7.8%の数字が示されている。具体的な手当てについては、原則として基本診療料で対応する方向性となってきており、歯科では「初・再診料」に必要な点数を上乗せすることになる。議論されてきた高額投資対応を診療報酬とは別建てで行うという案については、仕組みの複雑さ等から診療側委員、支払側委員の双方で反対意見が大勢を占め、8%増税時には見送られる模様。
方向性は見えてきたものの、高額投資について個別項目による手当てを実施するかどうか、また具体的に財源規模をどの程度と見積もるか等、今後さらなる議論が行われる。
>>歯科に関してですが、簡潔にいうと、消費税の増税分に対して、「初・再診料」に必要な点数を上乗せすることで対応すると捉えていいかと思います。この案件も含め、分科会で議題にあがったことについてですが、
(1) 消費税対応分を基本診療料や調剤基本料に上乗せする
(2) それに加えて「高額投資」を実施した医療機関等への加算を創設する
(3) 税負担が大きいと考えられる点数項目に消費税対応分を上乗せする(高額投資が必要と考えられる点数項目に配慮する)
(4)1点単価に消費税対応分を上乗せする
このうち(1)は、引き上げ分を初再診料、入院基本料、特定入院料等に限って上乗せし、補填を医療機関経営の基礎収入に反映させるというもので、支払・診療各側から、この案に賛成する声があがった。同時に、(1)に重点を置きながらも(3)と組み合わせて上乗せ配分を行なってはどうかという意見も複数の委員から出た。(2)と(4)については否定的な意見が大勢を占めた。との事です。
厳密に言えば、歯科に関しては、治療に際し、材料代がかかる治療が非常に多く、これに対し「基本診療料」だけに上乗せをして、ほぼ全てのケースに対応するというのは、少し思うところもありますが、全ての人が納得のいく案というのは難しく、少しでも多くの人に納得のいく案を議論していってもらいたいです。今後も注目していきたいと思います。